この記事はおよそ15分で読めます
空は水彩画の「にじみ」や「透明感」をもっとも美しく表せる対象物だと思います。
空は季節や時間帯によって表情が大きく変わり、描くたびに違う表情を見せてくれますね。
特に、澄んだ夜空に満月が浮かぶ月夜に思わず足を止めて見上げてしまったりしたご経験、
ありませんか?
今回は、水彩画初心者の方にも描きやすい「夜空」をテーマに、塗り方やコツを、実際の制作過
程を交えてご紹介します。
夜空を描く ― 静けさを感じる水彩の青
今回描く夜空のひとつめは、雲のない澄んだ夜空をイメージして描きました。
使う色の数も敢えて抑えて描きました。
こんな夜空を描くときは、「静けさや深み」の表現に留意するのが良いんじゃないでしょうか。
水彩ならではの透明感を活かしながら、穏やかな月明かりの広がる空を描いてみました。
ポイントに気をつければ、初心者のかたでも比較的簡単ですよ。
ではここから、描き方を説明してまいりましょう。

① 下準備:紙と筆
空は広いです。
そして、この広い面をできるだけムラなく塗りたいと思います、特に雲のない空では。
そのためには、水彩紙の水張りは必須です。
水張りをすれば、水でぬれても紙が波打ちにくいですからね。
紙が波打つと、紙の凹んだ部分に絵の具が溜まり、色が濃くなります。
反対に凸になった部分は絵の具が少なくなり、色が薄くなります。
このようにして、ムラができてしまいます。
水張りのやり方は、下記の記事『初心者でも安心!失敗しない水張りのやり方完全ガイド』を、
ご覧になって参考にしてくださると嬉しいです。
因みに今回使った水彩紙は、ARCHES(アルシュ)の中目を使いました。
そして筆ですが、広い面を塗るので刷毛か大型の平筆を準備しましょう。
今回、僕は下の写真のような刷毛を使いました。

②夜空以外のところをマスキング
これも、夜空の部分をムラなく塗るための工夫です。
ムラなく塗るには、筆の運びを淀ませないようにすることも重要です。
広い画面の中で筆(刷毛)を「サーっ」とスムーズに運んで色を塗ります。
筆を途中で停めたり淀めたりしない方がムラを作らないためには良いことです。
「空の色を塗らない箇所」があると、そこを避けて塗りますので、どうしても筆が淀んでしまいます。
そういう箇所を気にせずに筆を使えるように、空以外のとこを予めマスキング(マスキングインクかマスキングテープ)します。


今回の絵ですと、月と森と建物の部分にです。
この部分にマスキングしておくと、気にせず空を「サーっ」と一気に塗ることができます。
③夜空の色を準備
まず、夜空に塗る色をタップリ用意しましょう。
塗っている途中で絵の具が切れてしまうのは良くないです。
色を塗っている途中で慌てて作り足すのは、色目が急に変わったりムラの原因になります。
今回は、ウルトラマリンライトをベース色にして、より夜の暗さを出すためにヴァンダイキブラウンを少し混ぜて、いわゆる“藍色”にして使いました。
今回は澄んだ夜空を描きたかったので透明度の高い絵の具を選びました。
ウルトラマリンライトとヴァンダイキブラウンはどちらも透明度の高い色です。

これをタップリ作っておきます。色皿に作っておくと良いと思います。
④ 色を塗る
いよいよ空の部分に色をぬります。
塗る直前に、空の部分を刷毛で水で濡らしておきます。
絵の具を置いた時に広がりやすくするためです。こうするとムラができにくいです。
紙がムラなく湿った状態になったら、色をのせる準備完了です。
予め③で用意しておいた色を刷毛に十分に含ませて空の部分を塗ります。
まず、月の部分の周囲は、月が輝いている様子を表すため月に近くなるほどに色が薄くなるようにグラデーションにしたいです。
なので、月から少し離れたところから周囲に刷毛を動かすように塗って行きます。
紙の湿り気に乗って月の方向にも絵の具が滲んでいきますので、自然なグラデーションにできます。
月から離れた箇所では刷毛を「サーっ」とスムーズに動かして塗っていきます。
⑤塗ったら、一度乾かします
乾かすのは自然乾燥が良いと思います。
紙が塗れている間は絵の具が動きます。
そしてじんわりと乾いて絵の具が動かなくなるまで自然乾燥させる方がムラが出にくいです。
ただし、一部の濡れ具合が他と異なっている場合は、ムラになりやすいのでご注意を。
急いでいる場合はヘヤードライヤーを使っても良いですが、ムラを避けるという意味では、
あまりお勧めしません。
⑥乾いたら、④⑤を繰り返します
一度塗りでは、ムラを避けつつ深みのある着色ができにくいです。
3~4回繰り返すと、ムラがなくなり深みのある色になっていきます。
繰り返す中で、地平線に近い箇所ほど濃く暗くすることで、自然な奥行きが生まれます。
濃く暗い箇所を塗るときには、ウルトラマリンライトに対するヴァンダイキブラウンの量を増やした色を作りました。
紙の水分を保ちながら、濃淡をやさしくつけましょう。
⑦月と森と建物の部分のマスキングを剥がす
空の部分の色が塗り終えたら、マスキングを剥がします。
一旦マスキングを剥がしたら、もう一度マスキングするのは避けたい(森の水平線の境界部分や
塔の細かな部分を、剥がす前と全く同じに塗り直すのはテクニック的に難しいから)ので、空の
部分の色が「これで良し!」となるまで、マスキングは剥がさないようにしたいです。
マスキングを剥がしたら、月と森と建物の部分に紙の白が現れます。
⑧森の部分を塗ります
森は、遠景の森と近景の森がありますね。
水平線に近いところは遠景の森。画面の下になるほど、手前つまり近景の森です。
遠近感を感じるようには、遠景の森の部分はあまりエッジをハッキリさせない方が良いです
一方、近景の森の部分はところどころエッジを効かせた方がより近くに感じます。
ただ、エッジの効いた所ばかりが並んでしまうと、人によっては「煩く」感じるかたもいらっし
ゃると思いますので、ココは好みで適度にコントロールしてください。
.jpg)
そして、森の部分は月の光を受けて明るく輝く部分と、陰になるところを意識しながら色の濃
さをコントロールしましょう。
つまり、月の真下の部分は明るく。そこから周囲に離れるにつれて暗くします。
こうすること、月明かりに照らされて森が輝いている感じが出せます。
.jpg)
⑨建物の部分をぬります
この絵の最後の対象物、モスクです。
このモスクにはドームの部分に螺旋状の文様が白色で施されています。
ドーム全体としては球に近い形をしていますので、丁度ボールに斜め上から光りを当てた時の
ような光と陰に塗ろうと思いました。
これをムラなく塗りたかったので、白い文様の部分に予めマスキングしてドームを塗りました。
マスキングしたら、ドームの部分に水を塗ってから着色します。
月に向いている左斜め上の所を塗り残して、右斜め下に向けて暗く濃く塗ります。
また、ドーム以外の部分については、月に向いている方を明るく、反対側は暗く塗れば大丈夫
です。
.jpg)
作成チュートリアル動画
それでは、ココで、実際の制作経緯を動画でご覧いただこうと思います。
下のリンクをクリックください。
まとめ・・・夜空を描くことで感じる「水彩の魅力」
水彩の透明感が生む“静けさ”を楽しみましょう
夜空を描くとき、柔らかな青のにじみや透明感の重なりは水彩画の大きな魅力です。
筆の跡を残さず、静かな空気を画面に表すことで、透明で穏やかな時間が流れるような一枚に
なります。
丁寧な下準備が仕上がりを左右しますので手間を惜しまずに
水張りやマスキングといった工程は確かに手間です。めんどくさいと感じる向きもあろうかと
思います。
しかし、これを丁寧に行うことでムラを防ぎ、美しいグラデーションを実現できます。
特に夜空のような広い面では、下準備が作品全体の印象を決める大切なポイントです。
絵の具を惜しまず、たっぷりと使いましょう
夜空の深みを出すためには、途中で絵の具が切れないように十分な量を準備しておくことが
重要です。 またこれは色ムラを作らないためでもあります。
今回は、より透明感を出すために、透明度の高い色を選択して藍色を出しました。
ウルトラマリンとヴァンダイキブラウンはいずれも透明度の高い色です。
これらの組み合わせが生む“藍色”は、澄んで落ち着いた夜の空気を表現してくれます。
重ね塗りでムラを防ぎつつ奥行きをつくる
一度塗りで終えず、乾かしてから何度か重ねることで、色ムラ塗りムラを防ぐと同時に夜空に
深みが生まれます。
地平線に向かって徐々に濃くしていくと、遠近感と静謐さが自然に表現できます。
月明かりの配置が絵全体を引き立てる
月や建物、森の光と陰の関係を意識することで、画面全体にリズムが生まれます。
明暗のコントラストが強すぎないように注意し、月の光を感じる柔らかなトーンでまとめると
上品です。
“夜空”は初心者にもおすすめのテーマ
シンプルな構成ながら、水彩画の基本である「にじみ」「グラデーション」「透明感」のすべて
を練習できます。今回ご紹介した手順を通じて、水彩の楽しさを存分に味わっていただけると
うれしいです。
夜空を描くことは、単に風景を描くことではなく、心の中の静けさを映し出すことでもあると
思うんです。どうぞ、ご自身の感じた“夜の青”を、自由に紙の上で表現してみてください。
では、また。。。


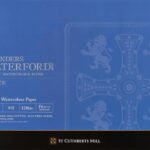


-485x366.jpg)
-485x322.jpg)
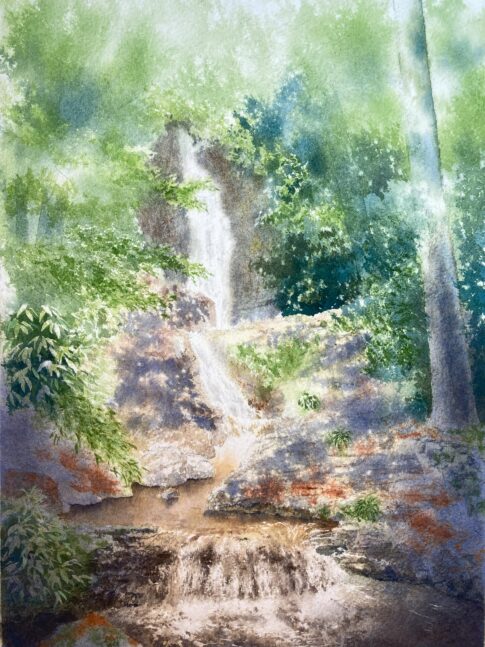

皆さんこんにちは Bakkyです
水彩画、、、たのしんでますか?
今回は、澄んだ月夜の描き方を解説したいと思います